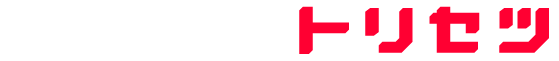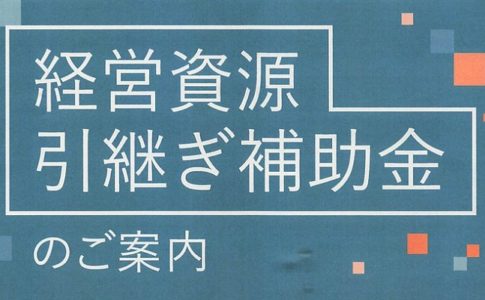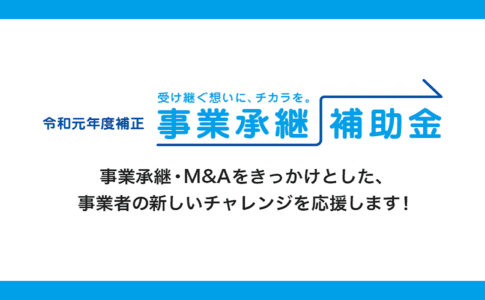最新記事 by 五十村 髙志 (全て見る)
- 【令和2年度補正】M&A費用を助成する経営資源引継ぎ補助金の活用法 - 2020年7月13日
- 【令和元年度補正】事業承継補助金を活用して世代交代する方法 - 2020年4月8日
- 【M&A投資】買収を成功させる投資判断基準 - 2020年3月21日
M&Aにおいて、最終契約の締結の前に、基本的な事項についてまとめた合意書を締結することがあります。
これを基本合意書といい、英語では、MOU(Memorandum of Understanding)と呼ばれています。 LOI(Letter of Intent)と言われることもありますが、こちらは正式には「意向表明書」のことですね。
基本合意書は、買収の意向や合意した事項について、当事者間で確認するためのもので、法的拘束力がない覚書です。では、このような”覚書”を、M&Aの際に作るのは一体なぜでしょうか?
さて今回は、M&A時に必要な基本合意書について、ご紹介いたします。
- 会社売却や企業買収を検討している人
- モノゴトを確実に前に進めたい人
- マリッジブルーになっている人
M&Aで基本合意書を作成する意味
M&Aで合意すべき事項は、⾮常に広範囲におよびます。そのプロセスは⻑く、時間もとてもかかります。また、当事者のM&Aへのスタンスも、時間の経過とともに変化することがあるから、なかなか大変なんです。
なので、お互いにもめないためにも、随時、書⾯にして、当事者同士が合意したことを明確にしながら、進めていくことが大切です。最終契約の段階で、すべての取引条件を一気に提⽰しても、まず合意に⾄ることはありませんよ。
最終局面で、当事者双⽅の認識があまりにも異なっていると、M&Aが破談になりかねません。これまでM&Aのために費やした膨大なエネルギーやコストが無駄になってしまうのは、いくらなんでも悲しすぎますよね。
売却側と買収側のM&Aの初期段階のスタンス
M&Aのプロセスが進むと、売り手は機密情報を開⽰することになります。売り手としても、買収希望企業が、M&Aに対して具体的な意思を⽰してもらわないと、社内情報を開⽰することに大きな抵抗があるものです。
当然ですが、実現可能性の⾼くないM&Aであれば、売り手としては次のステップに進みたくないものです。
- マネジメントインタビュー
- 経営者⾯談
- デュー・デリジェンス(DD)
特に、以上の面談を伴うステップについては、情報漏洩のリスクもあるため、売り手としてはとても神経質になっています。
一方で、買収希望企業としても、売り手が売却の意向や条件が固まっていない段階では、M&Aを具体的に検討して良いか、判断することができません。
特に、先程の面談を伴うステップでは、膨大なエネルギーや相当のコストがかかるため、売却の強い意思表示がないと、買収希望企業も次のステップに進みにくいのです。優先順位を下げられて、後回しにされてしまうこともままあります。
そのため、譲渡価額や特定の重要な取引条件などについて、互いに意思表示をした事項を明らかにしながら、プロセスを進めることが一般的になっています。


基本合意書の構成と独占交渉権
M&Aの基本合意書は、売り手と買収希望企業とが、合意に⾄った基本的な内容が記載されることになります。案件の個別事情よって内容は異なりますが、通常は以下の項目が記載されます。
- 取引基本条件(スキーム・対象・対価など)
- スケジュール(デュー・デリジェンスの期間や最終契約の時期など)
- 独占交渉権
- 役職員の処遇などの基本的な条件
- デュー・デリジェンスの協力義務
- 誓約事項
- 法的拘束⼒
- 秘密保持義務
- 費用負担
- 準拠法
- 裁判管轄
なお、基本合意書を締結すると、売り手は、買収希望企業との間に⼀定期間の独占交渉権を与えるのが一般的です。
買主候補会社としては、面談を伴うステップでは、莫大なエネルギーとコストを投入するため、検討を⾏っている期間は、独占交渉権を⼊⼿したいと考えるのです。


基本合意書には法的拘束⼒がない︕︖
M&Aの基本合意書には、法的拘束⼒がないのが一般的です。
というのも、基本合意書を締結する段階ではまだ対象会社の精査ができていないので、買収希望企業としては、法的拘束⼒を有する合意をすることができないのはやむを得ないことです。
「法的拘束⼒がないのであれば、基本合意書を締結しても意味ないじゃん」と思われるかもしれません。ただ、書⾯に記載する以上、事実上の拘束⼒はあります。
なぜなら、最終契約書において、基本合意書に規定しなかった条件を、追加・変更・削除することは、合理的な説明を要することになります。基本合意書には法的拘束⼒はありませんが、事実上の拘束⼒は存在するのです。
ここで、考え方をもう一歩前に進めてみますね。
ここまでお話しすると、基本合意の段階において、既にM&Aの交渉が始まっているに、お気づきいただいたと思います。M&Aを検討する際には、このことを深く認識したうえで書面を作成していく必要があります。




基本合意書への譲渡価額の記載方法
M&Aの譲渡価額の提示の仕方としては、二種類あります。
- 特定の⾦額
- 幅を持った金額
特定の⾦額を提⽰する場合は、売り手としては、金額基準が明確になるメリットがありますが、買収希望企業としては、⾦額に拘束⼒が⽣じてしまうため、容易に提⽰することができないものです。
一方で、買収希望企業としては、幅を持った金額を提示する⽅が、後から変更しやすいため、好ましいものです。売り手にとっては、金額が意思決定の重要な指標となることが多いため、下限があまりにも低すぎると、交渉の土俵にあがらないこともありえます。通常は、上限額は期待できず、下限額となる可能性が⾼いと考えるのものなので、買収意欲の⾼い企業は、下限額をあまりに低く設定することは好ましいことではありません。
デュー・デリジェンス後の譲渡価額の修正
提案した譲渡価額について、デュー・デリジェンス(DD)の結果によって変動しうる条項をよく見かけます。
売り手からすると、粗探しをして譲渡価額の引き下げを画策していると見えるかもしれません。しかしながら、買収希望企業としては、デュー・デリジェンス(DD)を実施していない段階において、価額を提⽰し、その後にまったく変更を認められないというのでは、意思表示が困難なものとなってしまいます。
売り手も買収希望企業も、希望する条件で、M&Aの実現可能性が⾼いのであれば、その条件を確保したうえで、積極的に次のステップに進みたいものです。互いに大きなビジョンを語り、積極的に意思表示をすることが、M&Aを成功させるコツかもしれません。


基本合意書と適時開示
基本合意書には、最終契約と同等の項目が盛り込まれていることが、おわかりになったと思います。ということは、基本合意書の締結は、契約内容についてほぼほぼ了承したということを意味します。
基本合意書を締結するとき、注意が必要なのが上場企業です。
上場企業の場合、金融商品取引所の定めに応じ、相手と基本合意書を取り交わすと、会社の情報を開示しなければいけないという規定があります。上場企業のM&Aは、株主や投資家の利益に大きな影響を及ぼす可能性があるからです。
適時開示をすると、その案件の存在や当事者が広く世間に知れわたることになります。そうなると、外部(取引先や社員)からの影響や反応が必ず生じます。これが話を進めるうえでの、大きな障害になることも懸念されます。
買収の意向が固まっていれば、情報を公開するというルールはわかりますが、不確定な状況の情報を出したくないという気持ちもあるものです。
では、このような場合はどのようにしたら良いでしょうか?
この場合、基本合意書を締結せずに、買収希望企業から売り手に対して、法的拘束⼒がないとされる意向表明書を差し⼊れます。⽂字通り、「買いますよ!」という意向を表明する書⾯のことです。
基本合意書でも意向表明でも、自分にとって有利にしようという気持ちはわかります。ただ、相手に要求を呑んでもらおうとするばかりだと、交渉はうまく進まないものです。相手の気持ちや状況を鑑み、言葉にすることが適切かをよく判断し、書類を作成することが、M&Aを成功に導くカギだと思います。


- 基本合意書は、法的拘束力はないけど、拘束力はある!
- 自分の意思を表示しろ!
- 上場会社の場合、適時開示には気を付けろ!